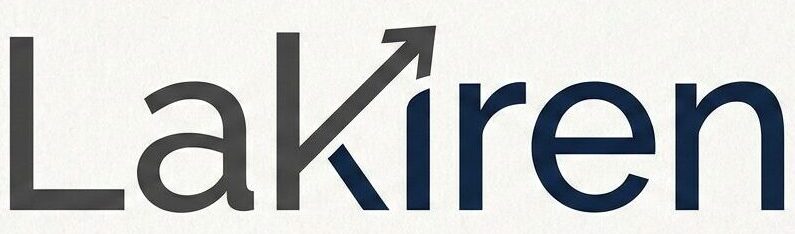2004年、Appleは1Uラックマウント筐体にPowerPC G5を載せた「Xserve G5」を投入した。UNIXベースのMac OS X Serverと組み合わせ、Web/メール/ファイル共有を“すぐ立てられる”ことを前面に出した製品だ。

デュアル2.0GHz(後期は2.3GHz)構成、ECCメモリ最大16GB、ホットスワップSATAは3ベイで、数字を並べれば典型的な当時の1Uだが、実機に触れた印象は少し違う。フロントのアルミフェイス、ベイのレバーの動き、そして管理ツールの素直さ。Linuxサーバに慣れた管理者にとっても、導入初日から役割を持たせやすい“敷居の低さ”があっただろう。

3ベイという割り切りは象徴的だ。G4世代の4ベイから後退した背景には、G5の発熱と1Uの薄さがある。前面からの吸気を厚く取り、風の通り道を優先した結果、ベイを1つ分あてがった。そう理解すると、設計全体の文脈が通る。運用時の肌感もそこに直結する。高負荷が続くとファンが躊躇なく全開に上がり、ラック全体の音の主役になる。静音・高密度・高性能の三立は難しい。それでも、GUIのサーバ管理ツールで役割を“ポチポチ”入れられる体験は強力で、中小規模の現場では「これで十分」という瞬間が確かにあった。
I/OはデュアルGigabit Ethernet、64bitのPCI-Xスロットなど手堅い構成。必要に応じてRAIDカードを追加し、SATAベイを束ねる。OSは10.3から10.4へ、最終的には10.5.8まで。スペック表の見栄えよりも、導入の早さと保守の見通しを優先した設計に見える。実際、HPCや教育機関での採用例もあり、“Macが端末以上の役割を担う”という試みは一定の説得力を持っていた。
短命だった理由と、その後

転機は2006年。AppleのIntel移行に合わせ、XserveはXeonベースへと世代交代する。冗長電源やFB-DIMMなど、サーバ然とした要件は整った一方で、“G5のXserve”はここで実質的に役割を終える。2010年末には、AppleがXserveの将来版を提供しない方針を明言。受注は2011年初頭で打ち切られ、代替としてMac Pro(Server構成)やMac mini Serverが案内された。ラックに純正の“Macサーバー”を並べる風景は、静かに幕を閉じる。
Xserve G5は、短命ゆえに“幻”と呼ばれる。しかし残ったのは、単なる一世代の製品ではない。1Uという制約の中で冷却と拡張のバランスをどう取るかという生々しい設計判断、専門職でなくてもサービスを立てられる運用体験、そして「Macでやってみる」という当時の勢いだ。ファンは吠え、ベイは3つ。それでも、ステータスLEDが並んで点るラックの前で、現場は確かに前へ進んでいた。あの短い季節を思い出すことは、今のサーバー設計や運用の“当たり前”を見直す小さなきっかけにもなるかもしれない。