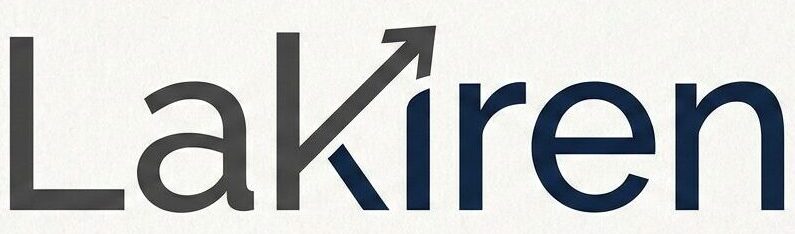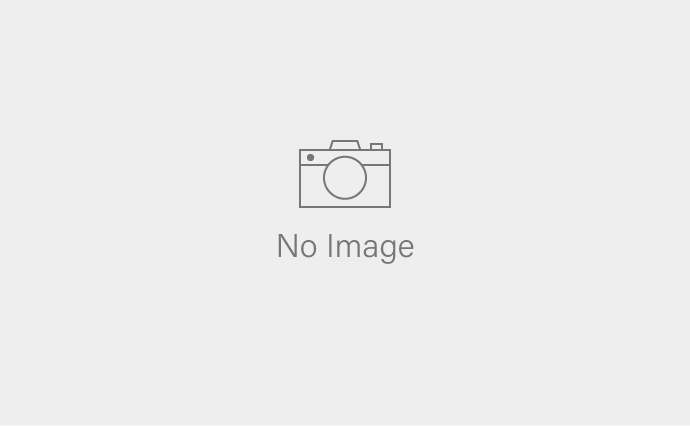生成AIとストック素材の境界が溶けつつある今、画像や図版、古典テキストをどう扱うかは、記事の信頼性そのものを左右する。そこで改めて確認したいのが「パブリックドメイン(Public Domain)」だ。しばしば“自由に使える”と要約されるが、より正確には「著作権の保護対象外、または保護期間が満了したため、誰でも許諾なく利用できる状態」を指す。ここで重要なのは、“著作権が切れていること”と“他の権利・規制がないこと”は別問題だ、という点である。肖像権やパブリシティ権、商標・意匠、機関ごとの利用ポリシーが並走し、記事の文脈によっては同じ素材でもリスクが変わる。

クリエイティブ・コモンズ・ジャパン公式サイト:https://creativecommons.jp/licenses/
日本法の実務的な目安として、個人の著作物は著作者の死後70年、法人名義や匿名・変名の著作物は公表後70年が基本線となる。(※匿名・変名作品は公表後70年が基本ですが、実名が判明・登録された場合は死後70年に切り替わります)
もっとも発表年や没年が不明なケース、戦時加算の扱い、編集著作物のように権利関係が層になっている例もある。素材を見つけた時点で“使える/使えない”と直感的に判断せず、必ず一次的な説明ページや注記まで辿ることが、後の差し替えや法務確認を最小化する近道だ。
パブリックドメインと混同されがちな概念に「CC0(クリエイティブ・コモンズ・ゼロ)」がある。こちらは、権利者が自発的に権利主張を放棄し、世界的にPD相当として扱ってほしいと宣言する“ツール”で、到達点としては似ているが、来歴が異なる。CC0の多くはクレジット義務がないとされるが、編集実務では出典の明示を基本運用にしておく方が良い。後工程での再配信や二次利用時に、出典や取得日の記録が効いてくるからだ。
素材の“探し場”としては、官公庁・公的機関、ミュージアムや図書館が公開するコレクション、そしてWikimedia Commonsのような大規模アーカイブが定番だ。ただし、いずれの場合も「サイト全体がPD」というわけではない。共同制作物や寄贈品が混ざることもあるし、ページ単位で個別の条件が付いている場合もある。Wikimedia Commonsであればファイルごとの説明ページに記されたライセンス欄と出典リンクが真実であり、ここを読まずに“フリー素材”と解釈するのは危うい。編集部としては、キャプションに出典名とライセンスの種別、取得日を添えるだけでなく、説明ページのスクリーンショットやPDFを証跡として保管しておくとよい。後からの異議申し立てやリンク切れに対し、判断根拠を提示できる。
実務の感触を共有するために、筆者が「幻のサーバーMacintosh『Xserve G5』を振り返ってみた」の執筆時に取ったやり方を紹介したい。
同記事では、まず画像検索でXserveの正面写真を当たり、Wikimedia Commonsのファイルページに入って確認を進めた。

ページを下へスクロールし、「ライセンス」セクションでパブリックドメインの根拠が明示されていること(PD-USGov-NASAの表示と注意書き)を確認。パブリックドメインで特に肖像権やNASAのロゴもないが、念のため画像のリンクをレイアウトに留めて掲載した。

「ネットにある=自由に使える」という誤解は根強い。転載を許諾しているだけの素材や、非商用限定、改変不可といった条件付きのライセンスは珍しくないし、SNS上の二次投稿は原権利者の意思と無関係なこともある。国や機関ごとに例外もある。たとえば同じ公的機関のサイトでも、他の組織が提供した画像が混ざっていたり、クレジットの方法だけが独特だったりする。
著作権が切れていても、人物の顔が大きく写っていればパブリシティ権の議論が発生し得るし、製品や建築物、ロゴの扱いは記事の文脈(推奨か批評か、広告に準じる使い方か)で評価が変わる。素材を“権利の束”として捉え、著作権以外の束が残っていないかを、最後まで疑い続ける姿勢が肝心だ。
結論を端的に言えば、パブリックドメインは“タダの素材箱”ではない。根拠を辿り、別権利の有無を見極め、出典を記す。この平凡な運用が積み重なるほど、記事は強くなる。Xserve回顧記事での実体験どおり、説明ページに戻って一次情報を押さえる習慣さえ身につければ、スピードと安全性は両立できる。メディア運営が長距離走である以上、法的な hygiene(衛生)を日々の作法として定着させることが、結局いちばんの近道だ。